2022年11月20日
◆未来塾(46) 昭和文化考・後半
ヒット商品応援団日記No811毎週更新) 2022.11,20

個人化社会の進行
1980年代注目すべきは社会構造が大きく転嫁していくことにある。例えば、当時核家族という言葉が使われるようになり、住まいも個室化するようになる。それを象徴するように、お化け番組と言われたTBSの「8時だよ全員集合」が1985年に終了する。更に年末のNHK紅白歌合戦は1984年78.1%を最後に右肩下がりとなる。つまり、家族での生活から、子供たちには個室があてがわれ、家族団欒という言葉は仕事なった。「豊かさ」が新たな社会構造の変化を促したと言うことである。
つまり、社会の単位が「家族」から個人へと変化し、私がそうした個人を「個族」と呼んだ。家族から個族への変化である。以降平成・令和と時代が変わっても「個人化」というライフスタイルの傾向は変わらない。勿論、家族の大切さ、家族価値の再考もあって個人と家族の間で揺れ動くことはあってもである。例えば、住宅メーカーの場合、「個室」はプライバシーを保つことになるのだが、閉ざされた空間であることから家族内の「会話」もまた乏しくなる。そうしたことからコミュニケーションが行えるリビングなどへの工夫なされるようになる。
消費においても、2000年代にはシングル女性の個人行動、特に旅行に注目が集まり、「ひとリッチ」という言葉も生まれる。更には、「一人鍋」がヒットし、あれこれちょっとづつ、個食、小食、が基本となる。こうした個人中心の価値観が広く浸透して行くこととなる。
一方、個人中心社会はあるいみで「バラバラ社会」のことでもあり、そのバラバラを解消するために「仲間社会」が生まれる。この仲間社会からは「いじめ」が生まれ、社会問題化したことは周知の通りである。あるいは地域のコミュニティの消滅にも向かわせ、大きな時代潮流の「負」の側面でもある。
「昭和」は新しい、おもしろい、珍しいか?

今「昭和」が若い世代において注目されている。リニューアルした西武園遊園地ではないが、昭和をテーマとしたテーマパークからクリームソーダがカフェの人気メニューになったように、新しい、おもしろい、珍しい「時代」として受け止められている。昭和を生きたシニア世代による郷愁としてではなく、現在のブームを創っているのは昭和の中にある「人間臭さ」「息遣い」にあるのではないかと思っている。
今や商業施設の賑わいづくりの定番にもなったレトロな雰囲気は若い世代にとってはまさに「新鮮」そのものであったということだ。渋谷パルコ、虎ノ門ヒルズ、渋谷横丁、心斎橋パルコ・・・・・・・・・・それら賑わいづくりのモデルになったのが吉祥寺のハーモニカ横丁である。賑わいとは街の息遣いの事である。詳しくは「未来の消滅都市論」を読んでほしいが、街の魅力がどのようにつくられてきたか一つのモデルとなっている。吉祥寺という街は都心・新宿と郊外・立川とのちゅかにある街で、消費のエリア間競争翻弄されてきた街であった。吉祥にには3つの百貨店があったが勝ち残ったのは東急百貨店のみで大型商業施設の多くは再編した経緯がある。街の活性化策として対象となったのが、駅前の一等地ハモニカ横丁であった。横丁に一歩入るとタイムスリップしたかのような商店・飲食店街が密集している路地がある。ハモニカ横丁と愛称されているが、そのハモニカの如く狭い数坪の店が並んでいる。餃子のみんみんのように、地元の人から愛されてきた店も多いが、一種猥雑な空気が漂う横丁路地裏にあって、なかにはおしゃれな立ち飲みショットバーや世界のビールやワインを飲ませるダイニングバーもあり、若い世代にはOLD NEW(古が新しい)といった受け止め方がなされている、そんな一角がある。人の温もりが直接感じられるそんな一角である。そんな時代の傾向を「観光地化」と名付けた。いわゆる都市観光である。観光の魅力は新しい、面白い、珍しい出来事体験である。日本アカデミー賞を受賞した「Always三丁目の夕日」に出てくる昭和の街並みに生きる三丁目の住民との出会いがあたかも追体験できるかのような錯覚を感じさせてくれる。その錯覚とは遠く懐かしさを感じさせてしまうもので、今や死語となってしまった父性と母性、お節介好きのおばさんに頑固親父、人間味を調節感じさせてくれる街。そんな当たり前の暮らし、日常の魅力である。三丁目の住人の一人になりたくで街を訪れるということである。[
「錯覚」という表現wp使ったが、ひとときの「昭和体験」をしたということである。これが観光地化の本質である。
昭和の風景、外へと向かうエネルギー 「食」
日本は地政学的にも多くの外国の人との交流によってモノや文化を取り入れてきた歴史がある。沖縄に今なお残るニライカナイ伝説では海の向こうには黄泉の国があると。海を通じて他国、他民族あるいは神と交流してきたと言う伝説である。面白いことにその沖縄には文明、文化の交差点を表した言葉が残っている。それは「チャンプルー」、様々のものが混ざり合った、一種の雑種文化の代名詞のようなものである。「食」で言えば、ゴーヤチャンプルーとか豆腐チャンプルーといった多くの食材を炒め合わせるチャンプルーのことである。
ところでその雑種文化から昭和の時代にもメガヒット商品が生まれている。コロナ禍によってインバウンド市場は激減してしまったが、訪日外国人が食べたい日本食NO1は、寿司でもすき焼きでもない、実はラーメンである。ラーメン市場も成熟市場であるが、本場中国麺の「日本化」ではない。ある意味、「和食」と“いう固有な世界と同じあり方、オリジナリティのある世界にまで進化した「食」である。少なくとも海外からのラーメン認識はそうである。極論かもしれないが、日本において和食がネイティブフーズだとするならば、ラーメンもネイティブフーズと考えても良いのではないかと思う。
雑居から雑種への進化については分かりやすい事例があっる。中国四川料理を日本に持ち込んだ珍県民が次のように言っている。
「私の中華料理少しウソある。でもそれいいウソ。美味しいウソ」と、日本の味覚に合わせたアレンジを行った。」
現在の日本では当たり前になっている「回鍋肉にキャベツを入れる」「ラーメン風担担麺(中国では汁なしが一般的)」「エビチリソースの調味にトマトケチャップ」、「麻婆豆腐には豚挽肉と長ネギ」というレシピは、建民が日本で始めたものだと言われている。例えば、麻婆豆腐は中国では山椒が効いていて「麻」はしびれるという意味。このアレンジこそが今日の日本での中国料理、とりわけ四川料理の普及に多大なる効果を発揮することになった。エビチリのトマトケチャップアレンジについては、中国本土でも、現在はそのような料理が見受けられると、陳建一が見聞したという。
こうした「進化」した食で世界を席巻したのはやはりラーメンになるであろう。ブランド化されたラーメン専門店は世界各地に進出し、インバウンド市場の多くは本場日本のラーメンを食べたいという訪日外国人が多く存在しているという。
昭和の風景、内へと向かうエネルギー 「食」

昭和の「食」でブームとなっているものに喫茶店の「クリームソーダ」や「ナポリタン」ががあるが、同じラーメンで言うならば「町中華」となる。ブランド化されたラーメン専門店ではなく、住宅地などどに少し前まではどこにでもあったあの町中華である。定番メニューで言えば「醤油ラーメンとなるが、手軽で安く食べ飽きないラーメンである。なるとにシナチク、それに焼き豚・・・・・・そんなラーメンである。
また、同じ傾向にあるのが食堂である。ダイニングバーではなく、抜かしながらの亜北道である。青森には100年食堂として残ってはいるが、東京ではどんどん少なくなってしまった。町中華も食堂も後継者不足から絶滅危惧業態になってしまった。手間暇かけて作る食より、セントラルキッチンで作られたチェーン業態の方が「経営」としては合理的であるという考えから今や探すのに苦労するほどである。但し、後継者がいる店の場合は若い後継者のアイディアや工夫により同じラーメンであっても地域の顧客に合わせたメニュー開発により繁盛店になっている。
こうした絶滅危惧専門店の継承を図る動きもあるが、残念ながら次第に市場からは無くなっていくこととなる。
未来塾(1)(2)では昭和の出来事の中で注目すべき「コト起こし」を中心にその発想など学ぶべきことを取り上げてきたが、そうした中、今「昭和レトロ」がブームとなっている。その対象の中心は若いZ世代とその上のミレニアム世代である。昭和を生きた世代にとって、そんな出来事が過去あったなと少しの郷愁を感じるだけである。そうした「下山途中」の人間にとって「登山の風景」を語ることはいささか面映さを感じてしまう。今回は「昭和文化考」としてできる限り昭和という時代の雰囲気・空気感を想起できるような注目すべき事象を取り上げた。
体験としての「昭和」
実は若い世代に決定的に足りないのが「経験」「実感」である。「倍速世代」と言われるように、過剰情報を処理するために倍速処理する。映画であればラストシーン・結末を見てから観るか観ないかをを決めるように駆け足で登山しているように見える。駆け足にさせているのが経験不足、いや未経験を埋めるためであるように思える。そうした倍速行動を促す一つを私は「昭和体験」と呼んでみた。
昭和世代にとって時代の風景は荒廃の中からのスタートであった。生きることに必死ではあったが、決して暗くはなかった。それは今日より明日、明日より明後日と、希望の持てる時代、それを感じることができた時代であった。それを可能にしたのは、それまでの「価値観」が戦争によってことごとく壊され、新たな価値観が求められ、それらを創る川へと変化したからであった。ある意味「前例」などないゼロスタートであったからで、そこには自由に発想し、行動できる時代であった。映画「Always三丁目の夕日」ではないが、「貧しかったけれど夢があった」とは、「自由」があったと置き換えても構わない。
ビートルズの日本公演に刺激された日本のミュージシャンは多く、それはジャンルを超えたものであった。その刺激によってJPOPも生まれたように、多くの若い世代は自由に登山できた時代であった。こうした音楽の聴取者はラジオの深夜放送で育った。その代表的番組が1965年から始まった『オールナイトニッポン』である。今も継続放送されてはいるが、倍速世代はニコ動やTikTokへと移り、町中華のラーメン同様絶滅危惧番組に向かっている。勿論、この深夜番組からはあの中島みゆきや吉田拓郎が生まれたことは知らない。
ところでその「昭和体験」の楽しみ方であるが、その特徴の一つが「体験確認」、つまり体験の記録をとることにある。所謂インスタグラムなどで公開する「映える」記録である。それは新大久保の韓国街での新メニューを殺エルするのとほとんど変わらない。若い世代がハマっているクリームソーダも古びたレトロな喫茶店でのもので、食べたい理由は二番目でまずは写真を撮ることにある。新大久保のコリアンタウンもそうだが、観光地体験ということである。繰り返し食べにくる人間もいるとは思うが、倍速世代にとって「登山」は駆け足で登ることであり、今日はこの山、明日は・・・・と体験を重ねるということである。
1980年代に男社会・大人社会に対し挑戦的であった「オヤジギャル」とは異なり、倍速世代はおとなしい。
数年前から、SNSなどを中心に盛んに使われ始め、2021年の「新語・流行語大賞」ではトップ10候補の「ノミネート3されたキーワードに「推し活」がある。昭和世代にとってはまるでわからない概念であるが、「推し」の対象は、アイドルやお笑いタレント、アニメ、キャラクター、漫画、ゲームから、歴史や鉄道、スポーツなどと幅広く存在する。ファンやオタクとは異なり、さらに一歩進んだ概念である。
元々「推す」という言葉が発生したのは、あのアイドルグループ「AKB48」に遡れる。彼女達の熱狂的ファンは最も応援しているメンバーを「推しメン」(”推しメンバー”の略)や単に「推し」と呼ぶようになり、それがいつからか他のアイドルやアイドル以外のゲームやアニメキャラなどでも使われるようになり、現在はさらに発展して「推し活」となる。アキバの雑居ビルから生まれたAKB48については分析してきたので過去のブログを見ていただきたいが、AKB48せん風の凄さは理解いただけるであろう。その延長線上に「推し活」があるということである。そして、多くの「推し」の対象の一つに昭和レトロもあるということである。
「居心地の良さ」にレトロ時間がある
何故か喫茶店が若い世代にも「推し」の一つとなっている。少し暗い落ち着いた空間のレトロな喫茶店でクリームソーダを飲むのだが、映える写真を撮ることも目的の一つであるが、人気のスターバックスとは異なる「時間」を感じていると私は考えている。大仰に言えば歴史や伝統への興味であるが、「ゆっくりとした時間」過剰な情報が行き交う日常とは遮断した「時間」を求めてのことと思う。駆け足登山をする倍速世代に突tれも居心地の良いう「時間」があるということであろう。昭和世代にとっては慣れ親しんだいつもの喫茶店、そんな日常「時間」があるということである。
そんな喫茶店の一つとして若い世代に人気の街吉祥寺にモデルのような喫茶てrんを取り上げたことがあった、未来塾(1)では次のように書いたことがあった。
『吉祥寺に詳しい知人に聞いたところ昭和レトロな喫茶店にも若い世代の行列ができているとのこと。聞いてみると吉祥寺駅南口近くの喫茶店「ゆりあぺむぺる」。宮沢賢治の詩集『春と修羅』に登場する名前からつけた喫茶店である。変化の激しい吉祥寺にあって、実は1976年にオープンして以来ずっと変わらずこの場所にあり、地元の人に愛されている老舗喫茶店である。勿論、クリームソーダも人気のようだが、他にもチキンカレーなどフードメニューもあるとのこと。』
このように2つの世代が交差している店だが、共通していることは穏やかで居心地の良い時間があるということだ。その居心地の良さとは、昭和世代にとっては「日常」ではあっても、倍速世代にとっては未体験の休憩時間である。
昭和」探検隊

昭和を振り返ってみると今なお続くものもあれば既に無くなってしまったものもある。昭和という時代を終え30年度度経つが、倍速世代を中心に「昭和」の見直しが始まったという感がしてならない。それは単なるリバイバル・復興と言った「過去」の再生ではなく、「ニュー昭和」とでも言いたくなるようなことである。何故そうした発想が生まれたかは、このコロナ禍の2年半若い世代の「行動」を観てきたが、ウイルスの拡散という悪者説がマスメディアの定説となっていることに対し、それは間違いであるとブログを通じて書いてきた。結論から言えば、倍速世代にとって、例えば人流抑制の効果について「その根拠は何か」そして「それは合理的であるか」を問うているだけで多くのことを否定している訳ではない。例えば、路上呑みが問題であると多くのマスメディアは指摘していたが、「何故8時までの飲酒は良くて、それ以降は感染拡大になるのか。「その根拠は何か、科学的な説明。路上と言うオープンエアのもとでの
飲酒の方が感染拡大にはならないのでは」」と問うているのだ。路上飲みの風景は良いとは思わないが、合理的な価値観世代にとっては路上飲みの方がより健康的ではという考えである。詳しくはブログを再読してほしいが極めて素直で優しい世代である。
そして、これからどんな「ニュー昭和」が生まれていくか楽しみである。例えば、「昭和の街」と言っても町全体が残っている場所はほとんどない。多くは再開発されていて路地裏横丁に一部残るだけとなっている。あるとすれば観光地となった「谷根千」ぐらいであろう。その中心となっている谷中銀座商店は次のような理念を持って活動している。分かりやすいのでHPの一部を転載する。
『時代と共に激変する商流の中で、今、商店街の存在価値が問われています。 時代の流れに適応しながらも、古き良き商習慣を大切に、商店街という文化を次世代に残していく、それが私たちの使命だと考えています。』
「残したいのは商店街という文化である」と明言している。町歩きを通じた時代観察を始めて10数年経つが吉祥寺とともに回数多く訪れた街である。詳しくは「未来の消滅都市論」を呼んでいただきたいが、若い世代が好みそうな店などどんな変化があるかわからないが、倍速世代にとっても格好の探検できる街であろう。ある意味谷根千は都心でありながらここ一帯だけが開発から取り残された「地域」で、THE昭和とでも言いたくなるところである。
思い出消費と未来消費
2009年、リーマンショックの翌年低迷する景気にあって突如として過去を振り返る消費が市場の多くを占める年なった。バブル崩壊の1990年代にもこうした危機にあって同じような「過去回帰型消費が出没した。例えば2009年の日経BJのヒット商品番付では大ヒットではないが前頭に次のような商品が消費されていた。
『アタックNeo、ドラクエ9、ファストファッション、フィッツ、韓国旅行、仏像、新型インフル対策グッズ、ウーノ フォグバー、お弁当、THIS IS IT、戦国BASARA、ランニング&サイクリング、PEN E-P1、ザ・ビートルズリマスター盤CD、ベイブレード、ダウニー、山崎豊子、1Q84、ポメラ、けいおん!、シニア・ビューティ、蒸気レスIH炊飯器、粉もん、ハイボール、sweet、LABII日本総本店、い・ろ・は・す、ノート、』
デフレが加速する中、復刻、リバイバル、レトロ、こうしたキーワードがあてはまる商品が前頭に並んでいる。花王の白髪染め「ブローネ」を始めとした「シニア・ビューティ」をテーマとした青春フィードバック商品群。1986年に登場したあのドラクエの「ドラクエ9」は出荷本数は優に400万本を超えた。居酒屋の定番メニューとなった、若い世代にとって温故知新であるサントリー角の「ハイボール」。私にとって、知らなかったヒット商品の一つであったのが、現代版ベーゴマの「ベイブレード」で、2008年夏の発売以来1100万個売り上げたお化け商品である。この延長線上に、東京台場に等身大立像で登場した「機動戦士ガンダム」や神戸の「鉄人28号」に話題が集まった。あるいは、オリンパスの一眼レフ「PEN E-P1」もレトロデザインで一種の復刻版カメラだ。売れない音楽業界で売れたのが「ザ・ビートルズ リマスター版CD」であり、同様に売れない出版業界で売れたのが山崎豊子の「不毛地帯」「沈まぬ太陽」で共に100万部を超えた。
ヒット消費の中心は団塊世代、下山途中の世代であるが、若い世代にもそうした消費のの傾向は広がっていった。
今回の昭和レトロブームはコロナ禍という「危機」による時代背景があることは事実であるが、倍速世代を中心とした若い世代へと広がっていくのかというと少し異なるものと考えている。倍速世代にとっての「昭和」は過去ではなく、過去の中に「未来」を観ているような気がしてならない。その「未来」とは未体験への興味・関心からであるが、これから小さなヒット商品が生まれてくると予測される。

そうしたヒット商品の多くはそのデザインにある。今流行っている家電商品の一つにアラジンのトースターがある。アラジンといえば、下山途中のシニア世代にとってはあのストーブのアラジンである。そのアラジンのトースターは機能も進化しているが、やはりそのデザインにある。丸みを帯びたレトロタイプである。
ところで「文化」は継承され時代に即した「何か」を取り入れ進化し、次代へと向かう。昭和という時代の雰囲気・空気感を思い起こしてもらいために主な出来事を選んできたが、中でもヒットが生まれるものの一つが「昭和歌謡」であろう。前述の阿久悠に代表される歌謡曲もそうだが、沢田研二の「勝手にしやがれ」にも注目が集まれ、現役である沢田研二のコンサートに倍速世代が聴きにくることも考えられる。また、かなり以前のブログに書いたことだが、休止中の「いきものがかり 」が確か青森でのコンサートで石川さゆりが歌った「津軽海峡・冬景色」をカバーしたという。例えば、中島みゆきが作詞作曲した「宙船(そらふね)」はTOKIOに歌わせたものがが、倍速世代のミュージシャンにカバー曲として提供するなどしたら日本の音楽界も活況を呈することであろう。
大きな転換期を迎えている
大きな転換期と言えば1990年代初頭のバブル崩壊を含めた1990年代であろう。それまでの昭和であった時代の価値観が大きく変わったことは周知恥の通りである。不動産神話をはじめ、潰れないと言われた大企業、金融企業、・・・・・製造業は中国へとその拠点を移し産業の空洞化も起きていた。実はそれ以上に大きな変化の予兆を指摘していたのが、団塊世代の名付け親で当時経済企画庁長官であった堺屋太一さんであった。生産年齢人口が減少へと変わったと警鐘を鳴らしたのだが、マスコミをはじめ殆ど注目されることはなかった。生産年齢人口とは働き・消費する人口のことであり、日本の国力基礎となる指標である。勿論その指標には少子高齢社会という問題も含まれている。
そして、1990年代を象徴するキーワードとして「デフレであったが、バブル崩壊後の国内消費を救ったのはデフレ企業であったが、視野を世界に広げてみると激烈な競争市場になっていた。実は数年前に「転換期」というテーマで日本産業の変化を調べたことがあった。その中で昭和と平成の違い・変化について次のように書いた。
『戦後の日本はモノづくり、輸出立国として経済成長を果たしてきたわけであるが、少なく とも10 年単位で見てもその変貌ぶりは激しい。例えば、産業の米と言わた半導体はその生産額は 1986年に米国を抜いて、世界一となった。しかし、周知のように現在では台湾、韓国等のメーカーが台頭し、 ランキングではNo1は米国のインテル、No2は韓国のSamsung で ある。世界のトップ10には東芝セミコンダクター1社のみとなっている。 あるいは重厚長大 産業のひとつである造船業を見ても、1970年代、80年代と2度にわたる「造船大不況」期を乗り 越えてきた。しかし、当時と今では、競争環境がまるで異なる。当時の日本は新船竣工量で5割 以上の世界シェアを誇り、世界最大かつ最強の造船国だった。しかし、今やNo1は中国、No2は 韓国となっている。 こうした工業、製造業の変化もさることながら、国内の産業も激変してきた。少し古いデータであ が、各産業の就業者数の 構成比を確認すればその激変ぶりがわかる。
第一次産業:1950年48.5%か1970年19.3%へ、2010年には4.2% 第二次産業:1950年15.8%か1970年26.1%へ、2010年には25.2% 第三次産業:1950年20.3%か1970年46.6%へ、2010年には70.6%』
周知のことであるが、世界との競争で唯一勝ち残ったのはトヨタをはじめとした自動車産業であった。一方欧米、特に米国においてはGAFAに代表されるIT企業が世界を席巻した。「IT」の場合、モノづくりは二義的なことでインターネットによる「情報活用」による今までなかった新しいビジネスである。
何故、GAFAのようなビジネスが生まれなかったのかと言えば、昭和の創業型経営者から平成のサラリーマン経営者へと変化し、資本のグローバル化の波に飲み込まれてしまい思い切った「新しい試み」に躊躇するいわばサラリーマン経営者になってしまったということがその要因の一つであろう。もう一つ挙げるとすれば「バブル後遺症」から脱却できなかったということだ。唯一創業型経営を続けているのはソフトバンクやユニクロであり、失敗を恐れない経営であることを見れば明らかであろう。
実はこうした失敗を恐れることを嫌い傾向は広く日本社会へと広がっている。リスクの少ない生き方、働き方、が求められ、出る杭いは打たれるではないが、そんな人材は極めて少ない社会となっている。ロシアによるウクライナ侵攻から始まった世界の「変化」を見てもわかるが、数年前までのグローバルビジネスとは異なる局面へと激変している。まるで欧米対ロシアと言ったブロック経済のような新たな「壁」がつくられつつある。戦後の昭和が「自由なビジネス」を求めて世界中くまなくセールスした時代であったが、「自由」を実現する苦労から、「壁」をどう壊していくか柔軟でしたたかなビジネスへの転換である。つまり、新たな「競争が始まっている。
もうひとつ時代の転換を感じさせる出来事が起きた。周知の安倍元総理銃撃事件である。その衝撃は容疑者の犯行の背景に旧統一教会への恨みがあったとの報道である。「まだ統一教会って活動してたのか!というのが率直な感想で、その名は霊感商法と共にメディアを通じて知っていた程度で、「何故」という思う疑念が起きた。これから社会的に問題である団体と政治との関係会えういは被害者の救済など議論されていくと思うが、戦後の「昭和」の裏側に潜む問題であり、「昭和」の影を避けて通ることの出来ない課題である。そして、こうした問題こそ「昭和世代」が責任をもって解決すべきことでもある。
それは何よりも「登山」途中の若いZ世代が自由に歩くことができる環境づくりでもある。消費だけでなく、広く新しい価値観のもとで新しい社会を創っていく世代であると確信をしているからだ。昭和世代が敗戦によって過去の「既成」から自由であったように、Z世代はバブル崩壊という敗戦にも似た転換期以降に生まれた。ある意味「昭和」という過去の既成から自由な世代ということだ。戦後の昭和世代が残したものはGDP世界3位の経済大国ではなく、既成からの「自由」であると考えるからだ。

そのZ世代が好きなバンドの一つに「いきものが」かり がある。その定番曲に「ブルーバード」(2008年)という曲がある。 人気アニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』の主題歌にもなった曲で、あああの曲かと思う人も多いかと思う。この曲をキーワードとして言うならば、「自由への希求」であろう。「昭和」時代の価値観から離れ、「自由」を求める世代ということだ。つまり、新しい価値創造はこの世代から始まるといっても過言ではない。

個人化社会の進行
1980年代注目すべきは社会構造が大きく転嫁していくことにある。例えば、当時核家族という言葉が使われるようになり、住まいも個室化するようになる。それを象徴するように、お化け番組と言われたTBSの「8時だよ全員集合」が1985年に終了する。更に年末のNHK紅白歌合戦は1984年78.1%を最後に右肩下がりとなる。つまり、家族での生活から、子供たちには個室があてがわれ、家族団欒という言葉は仕事なった。「豊かさ」が新たな社会構造の変化を促したと言うことである。
つまり、社会の単位が「家族」から個人へと変化し、私がそうした個人を「個族」と呼んだ。家族から個族への変化である。以降平成・令和と時代が変わっても「個人化」というライフスタイルの傾向は変わらない。勿論、家族の大切さ、家族価値の再考もあって個人と家族の間で揺れ動くことはあってもである。例えば、住宅メーカーの場合、「個室」はプライバシーを保つことになるのだが、閉ざされた空間であることから家族内の「会話」もまた乏しくなる。そうしたことからコミュニケーションが行えるリビングなどへの工夫なされるようになる。
消費においても、2000年代にはシングル女性の個人行動、特に旅行に注目が集まり、「ひとリッチ」という言葉も生まれる。更には、「一人鍋」がヒットし、あれこれちょっとづつ、個食、小食、が基本となる。こうした個人中心の価値観が広く浸透して行くこととなる。
一方、個人中心社会はあるいみで「バラバラ社会」のことでもあり、そのバラバラを解消するために「仲間社会」が生まれる。この仲間社会からは「いじめ」が生まれ、社会問題化したことは周知の通りである。あるいは地域のコミュニティの消滅にも向かわせ、大きな時代潮流の「負」の側面でもある。
「昭和」は新しい、おもしろい、珍しいか?

今「昭和」が若い世代において注目されている。リニューアルした西武園遊園地ではないが、昭和をテーマとしたテーマパークからクリームソーダがカフェの人気メニューになったように、新しい、おもしろい、珍しい「時代」として受け止められている。昭和を生きたシニア世代による郷愁としてではなく、現在のブームを創っているのは昭和の中にある「人間臭さ」「息遣い」にあるのではないかと思っている。
今や商業施設の賑わいづくりの定番にもなったレトロな雰囲気は若い世代にとってはまさに「新鮮」そのものであったということだ。渋谷パルコ、虎ノ門ヒルズ、渋谷横丁、心斎橋パルコ・・・・・・・・・・それら賑わいづくりのモデルになったのが吉祥寺のハーモニカ横丁である。賑わいとは街の息遣いの事である。詳しくは「未来の消滅都市論」を読んでほしいが、街の魅力がどのようにつくられてきたか一つのモデルとなっている。吉祥寺という街は都心・新宿と郊外・立川とのちゅかにある街で、消費のエリア間競争翻弄されてきた街であった。吉祥にには3つの百貨店があったが勝ち残ったのは東急百貨店のみで大型商業施設の多くは再編した経緯がある。街の活性化策として対象となったのが、駅前の一等地ハモニカ横丁であった。横丁に一歩入るとタイムスリップしたかのような商店・飲食店街が密集している路地がある。ハモニカ横丁と愛称されているが、そのハモニカの如く狭い数坪の店が並んでいる。餃子のみんみんのように、地元の人から愛されてきた店も多いが、一種猥雑な空気が漂う横丁路地裏にあって、なかにはおしゃれな立ち飲みショットバーや世界のビールやワインを飲ませるダイニングバーもあり、若い世代にはOLD NEW(古が新しい)といった受け止め方がなされている、そんな一角がある。人の温もりが直接感じられるそんな一角である。そんな時代の傾向を「観光地化」と名付けた。いわゆる都市観光である。観光の魅力は新しい、面白い、珍しい出来事体験である。日本アカデミー賞を受賞した「Always三丁目の夕日」に出てくる昭和の街並みに生きる三丁目の住民との出会いがあたかも追体験できるかのような錯覚を感じさせてくれる。その錯覚とは遠く懐かしさを感じさせてしまうもので、今や死語となってしまった父性と母性、お節介好きのおばさんに頑固親父、人間味を調節感じさせてくれる街。そんな当たり前の暮らし、日常の魅力である。三丁目の住人の一人になりたくで街を訪れるということである。[
「錯覚」という表現wp使ったが、ひとときの「昭和体験」をしたということである。これが観光地化の本質である。
昭和の風景、外へと向かうエネルギー 「食」
日本は地政学的にも多くの外国の人との交流によってモノや文化を取り入れてきた歴史がある。沖縄に今なお残るニライカナイ伝説では海の向こうには黄泉の国があると。海を通じて他国、他民族あるいは神と交流してきたと言う伝説である。面白いことにその沖縄には文明、文化の交差点を表した言葉が残っている。それは「チャンプルー」、様々のものが混ざり合った、一種の雑種文化の代名詞のようなものである。「食」で言えば、ゴーヤチャンプルーとか豆腐チャンプルーといった多くの食材を炒め合わせるチャンプルーのことである。
ところでその雑種文化から昭和の時代にもメガヒット商品が生まれている。コロナ禍によってインバウンド市場は激減してしまったが、訪日外国人が食べたい日本食NO1は、寿司でもすき焼きでもない、実はラーメンである。ラーメン市場も成熟市場であるが、本場中国麺の「日本化」ではない。ある意味、「和食」と“いう固有な世界と同じあり方、オリジナリティのある世界にまで進化した「食」である。少なくとも海外からのラーメン認識はそうである。極論かもしれないが、日本において和食がネイティブフーズだとするならば、ラーメンもネイティブフーズと考えても良いのではないかと思う。
雑居から雑種への進化については分かりやすい事例があっる。中国四川料理を日本に持ち込んだ珍県民が次のように言っている。
「私の中華料理少しウソある。でもそれいいウソ。美味しいウソ」と、日本の味覚に合わせたアレンジを行った。」
現在の日本では当たり前になっている「回鍋肉にキャベツを入れる」「ラーメン風担担麺(中国では汁なしが一般的)」「エビチリソースの調味にトマトケチャップ」、「麻婆豆腐には豚挽肉と長ネギ」というレシピは、建民が日本で始めたものだと言われている。例えば、麻婆豆腐は中国では山椒が効いていて「麻」はしびれるという意味。このアレンジこそが今日の日本での中国料理、とりわけ四川料理の普及に多大なる効果を発揮することになった。エビチリのトマトケチャップアレンジについては、中国本土でも、現在はそのような料理が見受けられると、陳建一が見聞したという。
こうした「進化」した食で世界を席巻したのはやはりラーメンになるであろう。ブランド化されたラーメン専門店は世界各地に進出し、インバウンド市場の多くは本場日本のラーメンを食べたいという訪日外国人が多く存在しているという。
昭和の風景、内へと向かうエネルギー 「食」

昭和の「食」でブームとなっているものに喫茶店の「クリームソーダ」や「ナポリタン」ががあるが、同じラーメンで言うならば「町中華」となる。ブランド化されたラーメン専門店ではなく、住宅地などどに少し前まではどこにでもあったあの町中華である。定番メニューで言えば「醤油ラーメンとなるが、手軽で安く食べ飽きないラーメンである。なるとにシナチク、それに焼き豚・・・・・・そんなラーメンである。
また、同じ傾向にあるのが食堂である。ダイニングバーではなく、抜かしながらの亜北道である。青森には100年食堂として残ってはいるが、東京ではどんどん少なくなってしまった。町中華も食堂も後継者不足から絶滅危惧業態になってしまった。手間暇かけて作る食より、セントラルキッチンで作られたチェーン業態の方が「経営」としては合理的であるという考えから今や探すのに苦労するほどである。但し、後継者がいる店の場合は若い後継者のアイディアや工夫により同じラーメンであっても地域の顧客に合わせたメニュー開発により繁盛店になっている。
こうした絶滅危惧専門店の継承を図る動きもあるが、残念ながら次第に市場からは無くなっていくこととなる。
「下山からの風景」に学ぶ
未来塾(1)(2)では昭和の出来事の中で注目すべき「コト起こし」を中心にその発想など学ぶべきことを取り上げてきたが、そうした中、今「昭和レトロ」がブームとなっている。その対象の中心は若いZ世代とその上のミレニアム世代である。昭和を生きた世代にとって、そんな出来事が過去あったなと少しの郷愁を感じるだけである。そうした「下山途中」の人間にとって「登山の風景」を語ることはいささか面映さを感じてしまう。今回は「昭和文化考」としてできる限り昭和という時代の雰囲気・空気感を想起できるような注目すべき事象を取り上げた。
体験としての「昭和」
実は若い世代に決定的に足りないのが「経験」「実感」である。「倍速世代」と言われるように、過剰情報を処理するために倍速処理する。映画であればラストシーン・結末を見てから観るか観ないかをを決めるように駆け足で登山しているように見える。駆け足にさせているのが経験不足、いや未経験を埋めるためであるように思える。そうした倍速行動を促す一つを私は「昭和体験」と呼んでみた。
昭和世代にとって時代の風景は荒廃の中からのスタートであった。生きることに必死ではあったが、決して暗くはなかった。それは今日より明日、明日より明後日と、希望の持てる時代、それを感じることができた時代であった。それを可能にしたのは、それまでの「価値観」が戦争によってことごとく壊され、新たな価値観が求められ、それらを創る川へと変化したからであった。ある意味「前例」などないゼロスタートであったからで、そこには自由に発想し、行動できる時代であった。映画「Always三丁目の夕日」ではないが、「貧しかったけれど夢があった」とは、「自由」があったと置き換えても構わない。
ビートルズの日本公演に刺激された日本のミュージシャンは多く、それはジャンルを超えたものであった。その刺激によってJPOPも生まれたように、多くの若い世代は自由に登山できた時代であった。こうした音楽の聴取者はラジオの深夜放送で育った。その代表的番組が1965年から始まった『オールナイトニッポン』である。今も継続放送されてはいるが、倍速世代はニコ動やTikTokへと移り、町中華のラーメン同様絶滅危惧番組に向かっている。勿論、この深夜番組からはあの中島みゆきや吉田拓郎が生まれたことは知らない。
ところでその「昭和体験」の楽しみ方であるが、その特徴の一つが「体験確認」、つまり体験の記録をとることにある。所謂インスタグラムなどで公開する「映える」記録である。それは新大久保の韓国街での新メニューを殺エルするのとほとんど変わらない。若い世代がハマっているクリームソーダも古びたレトロな喫茶店でのもので、食べたい理由は二番目でまずは写真を撮ることにある。新大久保のコリアンタウンもそうだが、観光地体験ということである。繰り返し食べにくる人間もいるとは思うが、倍速世代にとって「登山」は駆け足で登ることであり、今日はこの山、明日は・・・・と体験を重ねるということである。
1980年代に男社会・大人社会に対し挑戦的であった「オヤジギャル」とは異なり、倍速世代はおとなしい。
数年前から、SNSなどを中心に盛んに使われ始め、2021年の「新語・流行語大賞」ではトップ10候補の「ノミネート3されたキーワードに「推し活」がある。昭和世代にとってはまるでわからない概念であるが、「推し」の対象は、アイドルやお笑いタレント、アニメ、キャラクター、漫画、ゲームから、歴史や鉄道、スポーツなどと幅広く存在する。ファンやオタクとは異なり、さらに一歩進んだ概念である。
元々「推す」という言葉が発生したのは、あのアイドルグループ「AKB48」に遡れる。彼女達の熱狂的ファンは最も応援しているメンバーを「推しメン」(”推しメンバー”の略)や単に「推し」と呼ぶようになり、それがいつからか他のアイドルやアイドル以外のゲームやアニメキャラなどでも使われるようになり、現在はさらに発展して「推し活」となる。アキバの雑居ビルから生まれたAKB48については分析してきたので過去のブログを見ていただきたいが、AKB48せん風の凄さは理解いただけるであろう。その延長線上に「推し活」があるということである。そして、多くの「推し」の対象の一つに昭和レトロもあるということである。
「居心地の良さ」にレトロ時間がある
何故か喫茶店が若い世代にも「推し」の一つとなっている。少し暗い落ち着いた空間のレトロな喫茶店でクリームソーダを飲むのだが、映える写真を撮ることも目的の一つであるが、人気のスターバックスとは異なる「時間」を感じていると私は考えている。大仰に言えば歴史や伝統への興味であるが、「ゆっくりとした時間」過剰な情報が行き交う日常とは遮断した「時間」を求めてのことと思う。駆け足登山をする倍速世代に突tれも居心地の良いう「時間」があるということであろう。昭和世代にとっては慣れ親しんだいつもの喫茶店、そんな日常「時間」があるということである。
そんな喫茶店の一つとして若い世代に人気の街吉祥寺にモデルのような喫茶てrんを取り上げたことがあった、未来塾(1)では次のように書いたことがあった。
『吉祥寺に詳しい知人に聞いたところ昭和レトロな喫茶店にも若い世代の行列ができているとのこと。聞いてみると吉祥寺駅南口近くの喫茶店「ゆりあぺむぺる」。宮沢賢治の詩集『春と修羅』に登場する名前からつけた喫茶店である。変化の激しい吉祥寺にあって、実は1976年にオープンして以来ずっと変わらずこの場所にあり、地元の人に愛されている老舗喫茶店である。勿論、クリームソーダも人気のようだが、他にもチキンカレーなどフードメニューもあるとのこと。』
このように2つの世代が交差している店だが、共通していることは穏やかで居心地の良い時間があるということだ。その居心地の良さとは、昭和世代にとっては「日常」ではあっても、倍速世代にとっては未体験の休憩時間である。
昭和」探検隊

昭和を振り返ってみると今なお続くものもあれば既に無くなってしまったものもある。昭和という時代を終え30年度度経つが、倍速世代を中心に「昭和」の見直しが始まったという感がしてならない。それは単なるリバイバル・復興と言った「過去」の再生ではなく、「ニュー昭和」とでも言いたくなるようなことである。何故そうした発想が生まれたかは、このコロナ禍の2年半若い世代の「行動」を観てきたが、ウイルスの拡散という悪者説がマスメディアの定説となっていることに対し、それは間違いであるとブログを通じて書いてきた。結論から言えば、倍速世代にとって、例えば人流抑制の効果について「その根拠は何か」そして「それは合理的であるか」を問うているだけで多くのことを否定している訳ではない。例えば、路上呑みが問題であると多くのマスメディアは指摘していたが、「何故8時までの飲酒は良くて、それ以降は感染拡大になるのか。「その根拠は何か、科学的な説明。路上と言うオープンエアのもとでの
飲酒の方が感染拡大にはならないのでは」」と問うているのだ。路上飲みの風景は良いとは思わないが、合理的な価値観世代にとっては路上飲みの方がより健康的ではという考えである。詳しくはブログを再読してほしいが極めて素直で優しい世代である。
そして、これからどんな「ニュー昭和」が生まれていくか楽しみである。例えば、「昭和の街」と言っても町全体が残っている場所はほとんどない。多くは再開発されていて路地裏横丁に一部残るだけとなっている。あるとすれば観光地となった「谷根千」ぐらいであろう。その中心となっている谷中銀座商店は次のような理念を持って活動している。分かりやすいのでHPの一部を転載する。
『時代と共に激変する商流の中で、今、商店街の存在価値が問われています。 時代の流れに適応しながらも、古き良き商習慣を大切に、商店街という文化を次世代に残していく、それが私たちの使命だと考えています。』
「残したいのは商店街という文化である」と明言している。町歩きを通じた時代観察を始めて10数年経つが吉祥寺とともに回数多く訪れた街である。詳しくは「未来の消滅都市論」を呼んでいただきたいが、若い世代が好みそうな店などどんな変化があるかわからないが、倍速世代にとっても格好の探検できる街であろう。ある意味谷根千は都心でありながらここ一帯だけが開発から取り残された「地域」で、THE昭和とでも言いたくなるところである。
思い出消費と未来消費
2009年、リーマンショックの翌年低迷する景気にあって突如として過去を振り返る消費が市場の多くを占める年なった。バブル崩壊の1990年代にもこうした危機にあって同じような「過去回帰型消費が出没した。例えば2009年の日経BJのヒット商品番付では大ヒットではないが前頭に次のような商品が消費されていた。
『アタックNeo、ドラクエ9、ファストファッション、フィッツ、韓国旅行、仏像、新型インフル対策グッズ、ウーノ フォグバー、お弁当、THIS IS IT、戦国BASARA、ランニング&サイクリング、PEN E-P1、ザ・ビートルズリマスター盤CD、ベイブレード、ダウニー、山崎豊子、1Q84、ポメラ、けいおん!、シニア・ビューティ、蒸気レスIH炊飯器、粉もん、ハイボール、sweet、LABII日本総本店、い・ろ・は・す、ノート、』
デフレが加速する中、復刻、リバイバル、レトロ、こうしたキーワードがあてはまる商品が前頭に並んでいる。花王の白髪染め「ブローネ」を始めとした「シニア・ビューティ」をテーマとした青春フィードバック商品群。1986年に登場したあのドラクエの「ドラクエ9」は出荷本数は優に400万本を超えた。居酒屋の定番メニューとなった、若い世代にとって温故知新であるサントリー角の「ハイボール」。私にとって、知らなかったヒット商品の一つであったのが、現代版ベーゴマの「ベイブレード」で、2008年夏の発売以来1100万個売り上げたお化け商品である。この延長線上に、東京台場に等身大立像で登場した「機動戦士ガンダム」や神戸の「鉄人28号」に話題が集まった。あるいは、オリンパスの一眼レフ「PEN E-P1」もレトロデザインで一種の復刻版カメラだ。売れない音楽業界で売れたのが「ザ・ビートルズ リマスター版CD」であり、同様に売れない出版業界で売れたのが山崎豊子の「不毛地帯」「沈まぬ太陽」で共に100万部を超えた。
ヒット消費の中心は団塊世代、下山途中の世代であるが、若い世代にもそうした消費のの傾向は広がっていった。
今回の昭和レトロブームはコロナ禍という「危機」による時代背景があることは事実であるが、倍速世代を中心とした若い世代へと広がっていくのかというと少し異なるものと考えている。倍速世代にとっての「昭和」は過去ではなく、過去の中に「未来」を観ているような気がしてならない。その「未来」とは未体験への興味・関心からであるが、これから小さなヒット商品が生まれてくると予測される。

そうしたヒット商品の多くはそのデザインにある。今流行っている家電商品の一つにアラジンのトースターがある。アラジンといえば、下山途中のシニア世代にとってはあのストーブのアラジンである。そのアラジンのトースターは機能も進化しているが、やはりそのデザインにある。丸みを帯びたレトロタイプである。
ところで「文化」は継承され時代に即した「何か」を取り入れ進化し、次代へと向かう。昭和という時代の雰囲気・空気感を思い起こしてもらいために主な出来事を選んできたが、中でもヒットが生まれるものの一つが「昭和歌謡」であろう。前述の阿久悠に代表される歌謡曲もそうだが、沢田研二の「勝手にしやがれ」にも注目が集まれ、現役である沢田研二のコンサートに倍速世代が聴きにくることも考えられる。また、かなり以前のブログに書いたことだが、休止中の「いきものがかり 」が確か青森でのコンサートで石川さゆりが歌った「津軽海峡・冬景色」をカバーしたという。例えば、中島みゆきが作詞作曲した「宙船(そらふね)」はTOKIOに歌わせたものがが、倍速世代のミュージシャンにカバー曲として提供するなどしたら日本の音楽界も活況を呈することであろう。
大きな転換期を迎えている
大きな転換期と言えば1990年代初頭のバブル崩壊を含めた1990年代であろう。それまでの昭和であった時代の価値観が大きく変わったことは周知恥の通りである。不動産神話をはじめ、潰れないと言われた大企業、金融企業、・・・・・製造業は中国へとその拠点を移し産業の空洞化も起きていた。実はそれ以上に大きな変化の予兆を指摘していたのが、団塊世代の名付け親で当時経済企画庁長官であった堺屋太一さんであった。生産年齢人口が減少へと変わったと警鐘を鳴らしたのだが、マスコミをはじめ殆ど注目されることはなかった。生産年齢人口とは働き・消費する人口のことであり、日本の国力基礎となる指標である。勿論その指標には少子高齢社会という問題も含まれている。
そして、1990年代を象徴するキーワードとして「デフレであったが、バブル崩壊後の国内消費を救ったのはデフレ企業であったが、視野を世界に広げてみると激烈な競争市場になっていた。実は数年前に「転換期」というテーマで日本産業の変化を調べたことがあった。その中で昭和と平成の違い・変化について次のように書いた。
『戦後の日本はモノづくり、輸出立国として経済成長を果たしてきたわけであるが、少なく とも10 年単位で見てもその変貌ぶりは激しい。例えば、産業の米と言わた半導体はその生産額は 1986年に米国を抜いて、世界一となった。しかし、周知のように現在では台湾、韓国等のメーカーが台頭し、 ランキングではNo1は米国のインテル、No2は韓国のSamsung で ある。世界のトップ10には東芝セミコンダクター1社のみとなっている。 あるいは重厚長大 産業のひとつである造船業を見ても、1970年代、80年代と2度にわたる「造船大不況」期を乗り 越えてきた。しかし、当時と今では、競争環境がまるで異なる。当時の日本は新船竣工量で5割 以上の世界シェアを誇り、世界最大かつ最強の造船国だった。しかし、今やNo1は中国、No2は 韓国となっている。 こうした工業、製造業の変化もさることながら、国内の産業も激変してきた。少し古いデータであ が、各産業の就業者数の 構成比を確認すればその激変ぶりがわかる。
第一次産業:1950年48.5%か1970年19.3%へ、2010年には4.2% 第二次産業:1950年15.8%か1970年26.1%へ、2010年には25.2% 第三次産業:1950年20.3%か1970年46.6%へ、2010年には70.6%』
周知のことであるが、世界との競争で唯一勝ち残ったのはトヨタをはじめとした自動車産業であった。一方欧米、特に米国においてはGAFAに代表されるIT企業が世界を席巻した。「IT」の場合、モノづくりは二義的なことでインターネットによる「情報活用」による今までなかった新しいビジネスである。
何故、GAFAのようなビジネスが生まれなかったのかと言えば、昭和の創業型経営者から平成のサラリーマン経営者へと変化し、資本のグローバル化の波に飲み込まれてしまい思い切った「新しい試み」に躊躇するいわばサラリーマン経営者になってしまったということがその要因の一つであろう。もう一つ挙げるとすれば「バブル後遺症」から脱却できなかったということだ。唯一創業型経営を続けているのはソフトバンクやユニクロであり、失敗を恐れない経営であることを見れば明らかであろう。
実はこうした失敗を恐れることを嫌い傾向は広く日本社会へと広がっている。リスクの少ない生き方、働き方、が求められ、出る杭いは打たれるではないが、そんな人材は極めて少ない社会となっている。ロシアによるウクライナ侵攻から始まった世界の「変化」を見てもわかるが、数年前までのグローバルビジネスとは異なる局面へと激変している。まるで欧米対ロシアと言ったブロック経済のような新たな「壁」がつくられつつある。戦後の昭和が「自由なビジネス」を求めて世界中くまなくセールスした時代であったが、「自由」を実現する苦労から、「壁」をどう壊していくか柔軟でしたたかなビジネスへの転換である。つまり、新たな「競争が始まっている。
もうひとつ時代の転換を感じさせる出来事が起きた。周知の安倍元総理銃撃事件である。その衝撃は容疑者の犯行の背景に旧統一教会への恨みがあったとの報道である。「まだ統一教会って活動してたのか!というのが率直な感想で、その名は霊感商法と共にメディアを通じて知っていた程度で、「何故」という思う疑念が起きた。これから社会的に問題である団体と政治との関係会えういは被害者の救済など議論されていくと思うが、戦後の「昭和」の裏側に潜む問題であり、「昭和」の影を避けて通ることの出来ない課題である。そして、こうした問題こそ「昭和世代」が責任をもって解決すべきことでもある。
それは何よりも「登山」途中の若いZ世代が自由に歩くことができる環境づくりでもある。消費だけでなく、広く新しい価値観のもとで新しい社会を創っていく世代であると確信をしているからだ。昭和世代が敗戦によって過去の「既成」から自由であったように、Z世代はバブル崩壊という敗戦にも似た転換期以降に生まれた。ある意味「昭和」という過去の既成から自由な世代ということだ。戦後の昭和世代が残したものはGDP世界3位の経済大国ではなく、既成からの「自由」であると考えるからだ。

そのZ世代が好きなバンドの一つに「いきものが」かり がある。その定番曲に「ブルーバード」(2008年)という曲がある。 人気アニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』の主題歌にもなった曲で、あああの曲かと思う人も多いかと思う。この曲をキーワードとして言うならば、「自由への希求」であろう。「昭和」時代の価値観から離れ、「自由」を求める世代ということだ。つまり、新しい価値創造はこの世代から始まるといっても過言ではない。
タグ :Z世代
2022年11月13日
◆未来塾(46) 昭和文化考・前半
ヒット商品応援団日記No811毎週更新) 2022.11,13
未来塾の更新に時間が経昭和ってしまったが、戦後の発展成長の歴史に記憶すべき「昭和文化」、その風景について書き留めることとした。

ここ2回ほど未来塾では「下山から見える風景」として昭和の時代、特に昭和30年代にどんな出来事が生まれていたかを書いてきた。そこには「貧しくても夢があった」という言葉のように、何も無い時代に新しく何事かを「創る」無名の人たちがいたことを強く想起させるものであった。今日のライフスタイルの原型が江戸時代にあったように、わずか半世紀ほど前の「過去」を忘れてはならないという思いもあっていくつかの事例を挙げた。ただ同時にいま一つ時代の風景が鮮明にならないことも自覚した。それは昭和という時代の雰囲気、多くの人たちの息遣いが実感できていないということに辿り着いた。そうしたことから今回のテーマはいささか大仰ではあるが「昭和文化考」とした。
そして、この昭和文化を先導したのは戦後生まれの団塊世代であり、その先導を促進したのが雑誌とテレビ、ラジオというメディアであった。
戦前という過去からの解放が始まる
「敗戦」とはそれまでの多くの政治あるいは経済・社会の諸制度を根底から新たにつくり直すことでもあった。そして、そうしたつくり直しの第一歩が1964年(昭和39年)の東京オリンピックで復興のシンボルであったことは周知の通りである。一方、庶民の生活における復興は「闇市」から始まり、上野のアメ横もサラリーマンの街新橋の駅前ビルなど多くの商店街が売る側も買う側も自然発生的につくられた「市場」であった。(詳しくは「商店街から学ぶ」を参照してください)勿論、未整備な商業であり、今日で言うところの違法な商売もあったが、市場に集まる人たちによって過去に囚われい制度として今日に至る。ある意味で過去からの解放、自由な生き方・生活の仕方が始まったと言っても良いかと思う。つまり戦後文化はあらゆる意味で「自由」を求めるものとしてあった。「貧しくでも夢があった」とは、この「自由」な環境を背景としてある。つまりゼロからのスタートとは既成のない世界からのスタートであった。この「既成」からの自由であるとは、それまでの「大人」からの自由であった。前回書いたジブリ作品「となりのトトロ」における「大人」であり、子供たちは競って自分たちの「トトロ」を追い求めた。その子供とは戦後生まれの「若い世代」のことであった。
若者文化という言葉がメディアに登場する

1960年代と言えば戦後の荒廃がまだまだ残る中、高度経済成長が始まる時代である。ちなみに高度経済成長とは、1954年~1973年という19年間もの長い間の成長期である。よく中国の高度成長と比較されるが、一番低い年度で6.2%の成長でその多くは10%台という極めて高い経済成長を果たした時期である。収入も増えこの時代の消費の特徴は3種の神器と呼称された、3C(車、クーラー、カラーテレビ)が流行った時代である。生きてゆくことだけに必死であった時代を終え、豊かさを追い求める時代に入ったということである。実はその1964年に雑誌「平凡パンチ」が創刊される。貧しさから抜けはじめた時代を象徴するような雑誌であった。
出版社である平凡出版(現在のマガジンハウス)も戦後生まれの出版社で、当時の若い世代の興味関心事である車やファッション、さらには従来タブーとされてきたセクシーグラビアなどを取り上げ圧倒的な支持を得る。創刊から2年後の1966年には100万部を突破する。少しづつ経済的豊かさが進み、若い世代の関心はフッションへと向かう。
その中心は石津健介によるVANジャケットやJUNであった。こうした若者は当然であるが街へと向かう。1990年代後半渋谷109周辺が若い世代の表現舞台になったが、1964年当時は銀座のみゆき通がその舞台であった。その通りに集まる若者をメディアは通りの名前から「みゆき族」と呼んだ。当時の写真が残っていたので載せることにしたが、裾を短くしたコットンパンツに持ち物といえば紙袋であった。これが若い世代にとっての先端的なお洒落であった。1990年代渋谷109に集まったストリートファッションはガングロ・山姥ファッションであったが、みゆき族はその先駆けであった。
戦前の画一的な洋服から自由で思うままのファッションの源流はこのみゆき族から始まったと言っても過言ではない。米国文化の影響が色濃く残るが、一人ひとりの好みの表現、今日で言うところの「個性」への関心が生まれ、1970年代、1980年代へと日本のファッションへと向かう第一歩となった社会的事件であった。
こうした若者文化の事象は一例であって、以降の1970年代、1980年代という復興から成熟期、いや爛熟期へと向かうが、その原点は過去あった「既成」との決別で、振り返ってみればサブカルチャー。カウンターカルチャー誕生であったと言えなくはない。勿論、戦前にあった残すべき物の回復も必要であったが、この時代そうした整理を行う余裕はなかった。
新しい音楽への冒険が始まる

この時期1966年、日本全国を熱狂へと巻き込んだザ・ビートルズの最初で最後の来日公演が開催される。それまでのアイドル・バンドから本格的なアーティストへと変貌した、ビートルズにとってターニング・ポイントとも言える来日公演であった。
この公演が行われた場所は日本武道館で、日本武道振興の場所としてあり、ロック・コンサートなど行うとはといった批判もあった。ある意味で異例中の異例、それまでの「既成」を覆したミュージックイベントであった。
前座を務めたのは亡くなった内田裕也、尾藤勲、それにドリフターズであった。このビートルズショックは日本の若いミュージシャンをはじめ中高生にまでロックブーム、エレキブームを巻き起こす。
こうした社会的事件とでも表現したくなるような出来事の背景には、日本経済の生きる術、産業の転換が進んでいた。そもそも音楽、歌の発祥は労働歌にあった。ビートルズの音楽はある意味労働とは無縁の音楽である。
生きるため、その労働を癒し、明日へと労働の苦しさを忘れるために歌った音楽とは全く別次元の音楽であった。周知のように労働の苦しさ癒す音楽がブルースであったが、実はブルースは日本にも古来から存在していた。歌は自己投影、心の投影としてあるが、苦しさではなく、英国生まれのロックミュージックという新しい刺激、その「楽しさ」が若い世代の感性を揺さぶった。
日本産業の変化と共に歌も変化していく
少し古い比較データであるが次のような変化がわずか50数年の間に起きている。
□第一次産業(農林漁業)の従事者の割合は、
1955 年の 21.0% から 2008 年の 1.6%まで継続して低下。
□第二次産業(鉱業、建設業、製造業)の割合は、
1955 年の 36.8%から 1970 年には 46.4%まで上昇し、2008 年には 28.8%まで低下。
□第三次産業(サービス 業、卸売・小売業など)の割合は、
1955 年の 42.2%から 2008 年には 69.6%まで上昇。
この比較内容をコメントすると、1955年という年度はいわゆる高度経済成長期のスタートの時期であり、そのピークである1970年における製造業従事者の割合は46.4%で2008 年には 28.8%まで減少している。実はその差は大きく17.6%も減少し、バブル崩壊後の製造業の国内空洞化と言われている数字である。製造業による輸出立国と言われてきた日本とはまるで異なる産業構造に既に転換してしまっている事実である。円安による輸出が増えるどころか輸出入は赤字化し、海外投資などによる所得収入によってなんとか貿易を成立させているのが実態である。中国が世界の工場となって時間が経つが、最早従来のモノづくり貿易立国ではなくなっているということだ。失われた30年というが進む方向を見出せないままの30年はこうした産業構造からもわかる。

横道に逸れてしまったが、「歌」という視点から見ていくと、更にその変化がわかる。例えば、第一次産業(農林漁業)の労働歌と言えばその代表的な歌謡は民謡であろう。ソーラン節や大漁節などであるが、いまや日本の伝統芸能に組み込まれ、漁師町の日常に残る歌ではなくなっている。
第二次産業(鉱業、建設業、製造業)の労働歌・愛唱歌のなかに、ビートルズを含めた欧米の音楽が続々と日本に押し寄せる。そして、咀嚼しながら次第に日本固有の労働歌、というより愛唱歌が生まれてくる。「歌謡曲」の誕生である。
この歌謡曲の黄金期をつくった一人が阿久悠であった。この時代の日本レコード大賞受賞5回のヒットメーカーであり、小説家でもあり、無類の高校野球好きとして知られているが、実はヒット曲を調べていくと時代変化、揺れ動く様の「目撃者」であることがわかってくる。
阿久悠は大学卒業後広告代理店に勤めるが作詞家としての処女作はザ・スパイダースのグループ・サウンズデビュー曲「フリフリ」のB面である「モンキーダンス」(1965年(昭和40年)5月10日発売)グループサウンドブームの先駆けであったが、他にはフォークソングや後にJ POPへと繋がる音楽業界のまさに勃興機であった。
こうしたエレキバンドは勝ち抜きバンド合戦などその裾野が広がっていく。この裏には日本にエレキ部0むを巻き起こしたギターリスト寺内たけしの活躍持ってのことだが、音楽が一つのカルチャーとして一般庶民・和歌も鬼浸透していくことになる。このブームを更に進化させたのが、1971年にスタートする「スター誕生」というオーディション番組であった。今で言うところの素人発掘番組でスターを育てる趣旨であるが、こうして誕生したのが、桜田淳子、山口百恵、森昌子、新沼謙治などである。1970年代の日本歌謡界のスターが一つの文化を作ることとなる。ちなみに、審査員のヒットりに阿久悠も加わっている。
「スター誕生」という名称であるが、今日いうところのアイドルとは少し異なる存在であった。その象徴であったのが「山口百恵事件」であろう。山口百恵の風貌は素朴、純朴、誠実、といった言葉が似合う幼さが残る歌手としてデビューするのだが、そうした「少女」とは真逆な「大人」の性的さをきわどく歌い、そのアンビバランツな在り方が一つの独自世界をつくったスター(初期のアイドル)である。確か週刊誌であったと思うが、百恵が歌っている最中、風かなにかでスカートがめくれたパンチラ写真が掲載され話題となったことがあった。その時、百恵はその雑誌社に本気で抗議し、「少女」であることを貫いたのである。
そして、周知のように山口百恵は映画で共演した三浦友和と結婚するのだが、日本国中といったら言い過ぎであるが、その結婚に対して大きなブーイングが起きる。結果、「私のわがままな生き方を選びます」とコメントし、1980年に21歳という若さで引退する。百恵エピソードは数多く語られているが、1970年代という時代を駆け抜けた「少女アイドル」であった。
こうした経緯を見ていくと、のちのアイドルであるAKB48の指原莉乃が恋愛御法度の禁を破っで福岡に「転勤」し、復活したことと比べ大きな違いが見て取れる。
日本固有のサブカルチャーが手塚治虫によって誕生する
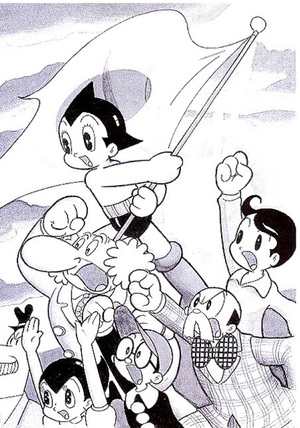
戦後のサブカルチャー誕生に欠かせない一人が漫画家手塚治虫である。戦前にもソンソ意欲さん漫画はあったが、戦後の新しい地平を確立したのが手塚出会った。周知のように1950年より漫画雑誌に登場、『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』といったヒット作を次々と手がける。
1963年、自作をもとに日本初となる30分枠のテレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』を制作、現代につながる日本のテレビアニメ制作に多大な影響を及ぼした。
と言うのも、子供向けの娯楽は戦前戦後とほとんど無かった時代であった。漫画のルーツを調べた専門家によればいわゆる紙芝居で戦後街頭紙芝居として復活する。(紙芝居の歴史は古く平安時代の『源氏物語絵巻』であるという説もある。その歴史を調べることは任にないことから、食べることすら容易では無かった戦後間もない頃の紙芝居を取り上げた。)
この紙芝居はTVが普及するにしたがって衰退していくのだが、多くの漫画家はこの紙芝居の愛好家であったと専門家は指摘している。そして、この紙芝居は東京のみならず関西でも広く浸透しており、大阪出身の手塚治虫もその一人であったという指摘もある。また、紙芝居の手法は間違いなくアニメ製作へと引き継がれていく。そして、少女漫画、劇画、ギャグ漫画、・・・・・・・多様なコンテンツの漫画が生まれるが、「あしたのジョー」や「巨人の星」といったヒット作を背景に、漫画雑誌が若い世代を中心に広く読まれるようになる。
漫画の歴史エオ分析することは私の任ではないので、明らかに時代を「感じさせてくれる」雑誌といえば、男性しであれば週刊少年マガジン(講談社 1959- 毎週水曜日発売)、
週刊少年サンデー(小学館 1959- 毎週水曜日発売)
週刊少年ジャンプ(集英社 1968- 毎週月曜日発売)
週刊少年チャンピオン(秋田書店 1969- 毎
少女向けでは、マーガレット(集英社 1963- 毎月5日20日発売)月2回刊)あるいはSho-Comi(小学館 1968- 毎月5日20日発売)月)などが発刊され漫画メディアは時代の主要メディアになっていく。そして、周知のように名称もコミック誌になり、テーマ別のコミック誌であるパチンコ、時代劇、ゴルフ、麻雀、釣り、など分化し、コミックマーケットという同人誌にまで進化していく。その進化の原点は1960年代にあったということである。
ちなみに1965年の「ハリスの旋風」を皮切りにマガジンの快進撃が始まり、「巨人の星」「あしたのジョー」の2大スポ根マンガで一気に少年雑誌としての地位を不動のものとした。その他にも「ゲゲゲの鬼太郎」「天才バカボン」なども連載を始め、1967年1月にはついに100万部を突破する。
新しい価値創造へと向かう70年代

1960年代は次の豊かさを実現するある意味環境づくり・助走の期間であった。その環境とは戦後生まれの団塊世代が本格的に働き、消費するという転換期を迎える。食べるために働いた時代で物の豊かさを求めた時代が60年代であったのに対し、70年代は物を求め物を満たすことが必要であった時代で、団塊の世代は「ニューファミリー」と呼ばれた。そして、今日を予見するような消費の「芽」が一斉に出てくる。
例えば、所得も増え単に物を満たすだけではない、そんな新しい価値をもった消費が現われてくる。1975年には便利さを売るセブンイレブンの1号店が誕生し、あのキャラクターのハローキティも生まれている。1976年には海外渡航者数が300万人を超える。こうした豊かさを背景に1980年代には多くの未来の芽が更に成長していく。
ファッション分野で言うと、80年代初頭には川久保玲や三宅一生さといった世界的なデザイナーによるデザイナーズ&キャラクターブランドが市場に新しい潮流をつくる。従来の男は男、女は女といった区別による考え方から、女性は男の良さを取り入れ、例えば肩パッドの入ったスーツを着こなし、男性は女性の柔らかなラインを取り入れたスーツを着るといった具合に。そうしたファッションの総称としてDCブランドと呼ばれ、セールを行う丸井には行列ができ社会的な注目を集める。つまり、物の価値がデザインといった情報的価値が求められていく時代の先駆けであった。
1980年代半ばそうした情報の消費を端的に表したのがロッテが発売したビックリマンチョコであった。シール集めが主目的で、チョコレートを食べずにゴミ箱に捨てて社会問題化した一種の事件が起きる。つまりチョコレートという物価値ではなく、シール集めという情報価値が買われていったということである。しかも、一番売れた「悪魔VS天使」は月間1300万個も売れたというメガヒット商品である。こうした現象も高度経済成長期ほどではないにしても安定成長となり、所得も着実に増え続けてきた背景がある。
「昭和文化」の爛熟期へと向かう
こうした消費変化を捉えたのがブランド戦略であった。モノ価値から情報価値への転換で、その中心は「女性」であった。1985年には男女雇用機会均等法が制定され、それまでの「女性らしく」あるいは男と女は違う」と言う旧来の固定観念が次から次へと変わっていく。DCブランドは更に個性的なブランドを生み出し競争はブランド間競争となる。そうした無名のブランド、小さなマンションメーカーと呼ばれたショップが原宿周辺に集まる。今日の竹下通りの原型がつくられていく。
こうしたファッションを中心としたテーマ集積を受けて、1980年代前半原宿の代々木公園横に設けられた歩行者天国で、ラジカセを囲み路上で踊るグループが出没する。次第に参加グループも多くなり、社会現象化する。いわゆる「竹の子族」の誕生である。1960年代銀座に集まった「みゆき族」に対し、踊りを組み込んだパフォーマンス集団へと進化していく。歩行者天国の廃止とともに竹の子族は消えていくのだが、ファッションの整地のポジションを確立していくこととなる。
1980年代は女性が社会という舞台に上がってきた転換期であった。団塊の世代はニューファミリーとして家庭づくりへと向かい、消費の舞台には上がってこなかったが、その下の世代は社会へと現われてくる。
この時代の空気感を作詞家阿久悠は沢田研二に「勝手にしやがれ」(1977年レコード大賞)を歌わせている。男と女の「すれ違い」をテーマとした歌である。
』 窓際に寝返りうって、背中できいている やっぱりお前は出て行くんだな・・・・・・』 別にふざけて 困らせたわけじゃない 愛というのに照れてただけだよ・・・・・・・
思い出していただけただろうか。後に阿久悠は「歌謡曲の時代」(新潮文庫)」の中で、”1970年代の男と女の気分が出ていると。更にその気分とは”真っ直ぐに、熱烈に愛することに照れてしまう”そんな気分を作詞したと書いている。

その象徴であると思うが、漫画家中尊寺ゆっこが描いたマンガで、従来男の牙城であった居酒屋、競馬場、パチンコ屋にOLが乗り込むといった女性の本音を描いたもので多くの女性の共感を得たマンガであった。その俗称が「オヤジギャル」。もう一つが物質的には満たされたお嬢様である二谷百合枝が郷ひろみとの出会いから結婚までを描いた「愛されれる理由」が75万部という1989年のベストセラーになる。つまり、物は充足するが何か心は満たされていない、そんなテーマの本であった。豊かさが次の段階へと進化してきたということである。新婚旅行から成田に帰国後離婚する華っぷりが多発し「成田離婚」として社会的な注目を集める。こうした背景には、女性からの一方的な期待、依存に応えることができないことが明らかになり、即離婚に移る女性が多く出現した結果でもあった。
昨年の東京オリンピック開催に際し、その理念とした多様性・平等といったことが話題となったが、既に1980年代においてその「芽」は出ていたと言うことである。
そして、1989年の暮れには株価は4万円近くにまで上がり、家計支出に占める食費や住居費といった生活必需品が50%を切り、娯楽や教育費の支出が50%を超える。後に「バブル期」と言われる時代である。
日本経済も日米摩擦はあるものの、造船竣工においては世界シェアー50%、半導体生産においても50%のシェアーを誇り経済は発展をしていた。そうした経済成長を背景に4月15日 に東京ディズニーランドが正式に開園する。また1987年にはリゾート法(総合保養地域整備法)が制定され、日本各地でいわゆるリゾート開発が行われる。多様な余暇産業が急速に進んだ。ゴルフ、スキー、マリーナ、リゾートホテル、といった大型施設を始めプール、スパ、ゲームセンター等が全国至る所で開発された。結果についてどうであったか、以前ブログにて書いたことがあるので今回は付け加えることはしないが、地方財政を悪化させ、過大なリゾート需要による実施、しかも画一的な開発によって・・・・・・・・・・結果は廃墟となり、いまなお野ざらしの状態の施設は多い。いわゆるリゾートバブルの崩壊である。こうした負の遺産も同時に起きていたことを忘れてはならないであろう。
なお、1989年4月初めての消費税3%がが導入される。このように日本経済が好調であったことから、大きな反対もなかった。
こうしたいわば転換期の日本については「転換期から学ぶ」(1)~(5)において主に生活価値観の変化、パラダイム転換について分析しているのでご参照ください。(後半へ続く)」
未来塾の更新に時間が経昭和ってしまったが、戦後の発展成長の歴史に記憶すべき「昭和文化」、その風景について書き留めることとした。

記憶の解凍
平凡パンチ、ビートルズ来日、アイドル、漫画、
新たな戦後文化の勃興、
昭和レトロブームの主人公、Z世代と昭和世代
新たな戦後文化の勃興、
昭和レトロブームの主人公、Z世代と昭和世代
ここ2回ほど未来塾では「下山から見える風景」として昭和の時代、特に昭和30年代にどんな出来事が生まれていたかを書いてきた。そこには「貧しくても夢があった」という言葉のように、何も無い時代に新しく何事かを「創る」無名の人たちがいたことを強く想起させるものであった。今日のライフスタイルの原型が江戸時代にあったように、わずか半世紀ほど前の「過去」を忘れてはならないという思いもあっていくつかの事例を挙げた。ただ同時にいま一つ時代の風景が鮮明にならないことも自覚した。それは昭和という時代の雰囲気、多くの人たちの息遣いが実感できていないということに辿り着いた。そうしたことから今回のテーマはいささか大仰ではあるが「昭和文化考」とした。
そして、この昭和文化を先導したのは戦後生まれの団塊世代であり、その先導を促進したのが雑誌とテレビ、ラジオというメディアであった。
戦前という過去からの解放が始まる
「敗戦」とはそれまでの多くの政治あるいは経済・社会の諸制度を根底から新たにつくり直すことでもあった。そして、そうしたつくり直しの第一歩が1964年(昭和39年)の東京オリンピックで復興のシンボルであったことは周知の通りである。一方、庶民の生活における復興は「闇市」から始まり、上野のアメ横もサラリーマンの街新橋の駅前ビルなど多くの商店街が売る側も買う側も自然発生的につくられた「市場」であった。(詳しくは「商店街から学ぶ」を参照してください)勿論、未整備な商業であり、今日で言うところの違法な商売もあったが、市場に集まる人たちによって過去に囚われい制度として今日に至る。ある意味で過去からの解放、自由な生き方・生活の仕方が始まったと言っても良いかと思う。つまり戦後文化はあらゆる意味で「自由」を求めるものとしてあった。「貧しくでも夢があった」とは、この「自由」な環境を背景としてある。つまりゼロからのスタートとは既成のない世界からのスタートであった。この「既成」からの自由であるとは、それまでの「大人」からの自由であった。前回書いたジブリ作品「となりのトトロ」における「大人」であり、子供たちは競って自分たちの「トトロ」を追い求めた。その子供とは戦後生まれの「若い世代」のことであった。
若者文化という言葉がメディアに登場する

1960年代と言えば戦後の荒廃がまだまだ残る中、高度経済成長が始まる時代である。ちなみに高度経済成長とは、1954年~1973年という19年間もの長い間の成長期である。よく中国の高度成長と比較されるが、一番低い年度で6.2%の成長でその多くは10%台という極めて高い経済成長を果たした時期である。収入も増えこの時代の消費の特徴は3種の神器と呼称された、3C(車、クーラー、カラーテレビ)が流行った時代である。生きてゆくことだけに必死であった時代を終え、豊かさを追い求める時代に入ったということである。実はその1964年に雑誌「平凡パンチ」が創刊される。貧しさから抜けはじめた時代を象徴するような雑誌であった。
出版社である平凡出版(現在のマガジンハウス)も戦後生まれの出版社で、当時の若い世代の興味関心事である車やファッション、さらには従来タブーとされてきたセクシーグラビアなどを取り上げ圧倒的な支持を得る。創刊から2年後の1966年には100万部を突破する。少しづつ経済的豊かさが進み、若い世代の関心はフッションへと向かう。
その中心は石津健介によるVANジャケットやJUNであった。こうした若者は当然であるが街へと向かう。1990年代後半渋谷109周辺が若い世代の表現舞台になったが、1964年当時は銀座のみゆき通がその舞台であった。その通りに集まる若者をメディアは通りの名前から「みゆき族」と呼んだ。当時の写真が残っていたので載せることにしたが、裾を短くしたコットンパンツに持ち物といえば紙袋であった。これが若い世代にとっての先端的なお洒落であった。1990年代渋谷109に集まったストリートファッションはガングロ・山姥ファッションであったが、みゆき族はその先駆けであった。
戦前の画一的な洋服から自由で思うままのファッションの源流はこのみゆき族から始まったと言っても過言ではない。米国文化の影響が色濃く残るが、一人ひとりの好みの表現、今日で言うところの「個性」への関心が生まれ、1970年代、1980年代へと日本のファッションへと向かう第一歩となった社会的事件であった。
こうした若者文化の事象は一例であって、以降の1970年代、1980年代という復興から成熟期、いや爛熟期へと向かうが、その原点は過去あった「既成」との決別で、振り返ってみればサブカルチャー。カウンターカルチャー誕生であったと言えなくはない。勿論、戦前にあった残すべき物の回復も必要であったが、この時代そうした整理を行う余裕はなかった。
新しい音楽への冒険が始まる

この時期1966年、日本全国を熱狂へと巻き込んだザ・ビートルズの最初で最後の来日公演が開催される。それまでのアイドル・バンドから本格的なアーティストへと変貌した、ビートルズにとってターニング・ポイントとも言える来日公演であった。
この公演が行われた場所は日本武道館で、日本武道振興の場所としてあり、ロック・コンサートなど行うとはといった批判もあった。ある意味で異例中の異例、それまでの「既成」を覆したミュージックイベントであった。
前座を務めたのは亡くなった内田裕也、尾藤勲、それにドリフターズであった。このビートルズショックは日本の若いミュージシャンをはじめ中高生にまでロックブーム、エレキブームを巻き起こす。
こうした社会的事件とでも表現したくなるような出来事の背景には、日本経済の生きる術、産業の転換が進んでいた。そもそも音楽、歌の発祥は労働歌にあった。ビートルズの音楽はある意味労働とは無縁の音楽である。
生きるため、その労働を癒し、明日へと労働の苦しさを忘れるために歌った音楽とは全く別次元の音楽であった。周知のように労働の苦しさ癒す音楽がブルースであったが、実はブルースは日本にも古来から存在していた。歌は自己投影、心の投影としてあるが、苦しさではなく、英国生まれのロックミュージックという新しい刺激、その「楽しさ」が若い世代の感性を揺さぶった。
日本産業の変化と共に歌も変化していく
少し古い比較データであるが次のような変化がわずか50数年の間に起きている。
□第一次産業(農林漁業)の従事者の割合は、
1955 年の 21.0% から 2008 年の 1.6%まで継続して低下。
□第二次産業(鉱業、建設業、製造業)の割合は、
1955 年の 36.8%から 1970 年には 46.4%まで上昇し、2008 年には 28.8%まで低下。
□第三次産業(サービス 業、卸売・小売業など)の割合は、
1955 年の 42.2%から 2008 年には 69.6%まで上昇。
この比較内容をコメントすると、1955年という年度はいわゆる高度経済成長期のスタートの時期であり、そのピークである1970年における製造業従事者の割合は46.4%で2008 年には 28.8%まで減少している。実はその差は大きく17.6%も減少し、バブル崩壊後の製造業の国内空洞化と言われている数字である。製造業による輸出立国と言われてきた日本とはまるで異なる産業構造に既に転換してしまっている事実である。円安による輸出が増えるどころか輸出入は赤字化し、海外投資などによる所得収入によってなんとか貿易を成立させているのが実態である。中国が世界の工場となって時間が経つが、最早従来のモノづくり貿易立国ではなくなっているということだ。失われた30年というが進む方向を見出せないままの30年はこうした産業構造からもわかる。

横道に逸れてしまったが、「歌」という視点から見ていくと、更にその変化がわかる。例えば、第一次産業(農林漁業)の労働歌と言えばその代表的な歌謡は民謡であろう。ソーラン節や大漁節などであるが、いまや日本の伝統芸能に組み込まれ、漁師町の日常に残る歌ではなくなっている。
第二次産業(鉱業、建設業、製造業)の労働歌・愛唱歌のなかに、ビートルズを含めた欧米の音楽が続々と日本に押し寄せる。そして、咀嚼しながら次第に日本固有の労働歌、というより愛唱歌が生まれてくる。「歌謡曲」の誕生である。
この歌謡曲の黄金期をつくった一人が阿久悠であった。この時代の日本レコード大賞受賞5回のヒットメーカーであり、小説家でもあり、無類の高校野球好きとして知られているが、実はヒット曲を調べていくと時代変化、揺れ動く様の「目撃者」であることがわかってくる。
阿久悠は大学卒業後広告代理店に勤めるが作詞家としての処女作はザ・スパイダースのグループ・サウンズデビュー曲「フリフリ」のB面である「モンキーダンス」(1965年(昭和40年)5月10日発売)グループサウンドブームの先駆けであったが、他にはフォークソングや後にJ POPへと繋がる音楽業界のまさに勃興機であった。
こうしたエレキバンドは勝ち抜きバンド合戦などその裾野が広がっていく。この裏には日本にエレキ部0むを巻き起こしたギターリスト寺内たけしの活躍持ってのことだが、音楽が一つのカルチャーとして一般庶民・和歌も鬼浸透していくことになる。このブームを更に進化させたのが、1971年にスタートする「スター誕生」というオーディション番組であった。今で言うところの素人発掘番組でスターを育てる趣旨であるが、こうして誕生したのが、桜田淳子、山口百恵、森昌子、新沼謙治などである。1970年代の日本歌謡界のスターが一つの文化を作ることとなる。ちなみに、審査員のヒットりに阿久悠も加わっている。
「スター誕生」という名称であるが、今日いうところのアイドルとは少し異なる存在であった。その象徴であったのが「山口百恵事件」であろう。山口百恵の風貌は素朴、純朴、誠実、といった言葉が似合う幼さが残る歌手としてデビューするのだが、そうした「少女」とは真逆な「大人」の性的さをきわどく歌い、そのアンビバランツな在り方が一つの独自世界をつくったスター(初期のアイドル)である。確か週刊誌であったと思うが、百恵が歌っている最中、風かなにかでスカートがめくれたパンチラ写真が掲載され話題となったことがあった。その時、百恵はその雑誌社に本気で抗議し、「少女」であることを貫いたのである。
そして、周知のように山口百恵は映画で共演した三浦友和と結婚するのだが、日本国中といったら言い過ぎであるが、その結婚に対して大きなブーイングが起きる。結果、「私のわがままな生き方を選びます」とコメントし、1980年に21歳という若さで引退する。百恵エピソードは数多く語られているが、1970年代という時代を駆け抜けた「少女アイドル」であった。
こうした経緯を見ていくと、のちのアイドルであるAKB48の指原莉乃が恋愛御法度の禁を破っで福岡に「転勤」し、復活したことと比べ大きな違いが見て取れる。
日本固有のサブカルチャーが手塚治虫によって誕生する
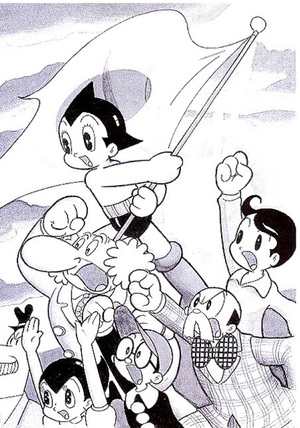
戦後のサブカルチャー誕生に欠かせない一人が漫画家手塚治虫である。戦前にもソンソ意欲さん漫画はあったが、戦後の新しい地平を確立したのが手塚出会った。周知のように1950年より漫画雑誌に登場、『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』といったヒット作を次々と手がける。
1963年、自作をもとに日本初となる30分枠のテレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』を制作、現代につながる日本のテレビアニメ制作に多大な影響を及ぼした。
と言うのも、子供向けの娯楽は戦前戦後とほとんど無かった時代であった。漫画のルーツを調べた専門家によればいわゆる紙芝居で戦後街頭紙芝居として復活する。(紙芝居の歴史は古く平安時代の『源氏物語絵巻』であるという説もある。その歴史を調べることは任にないことから、食べることすら容易では無かった戦後間もない頃の紙芝居を取り上げた。)
この紙芝居はTVが普及するにしたがって衰退していくのだが、多くの漫画家はこの紙芝居の愛好家であったと専門家は指摘している。そして、この紙芝居は東京のみならず関西でも広く浸透しており、大阪出身の手塚治虫もその一人であったという指摘もある。また、紙芝居の手法は間違いなくアニメ製作へと引き継がれていく。そして、少女漫画、劇画、ギャグ漫画、・・・・・・・多様なコンテンツの漫画が生まれるが、「あしたのジョー」や「巨人の星」といったヒット作を背景に、漫画雑誌が若い世代を中心に広く読まれるようになる。
漫画の歴史エオ分析することは私の任ではないので、明らかに時代を「感じさせてくれる」雑誌といえば、男性しであれば週刊少年マガジン(講談社 1959- 毎週水曜日発売)、
週刊少年サンデー(小学館 1959- 毎週水曜日発売)
週刊少年ジャンプ(集英社 1968- 毎週月曜日発売)
週刊少年チャンピオン(秋田書店 1969- 毎
少女向けでは、マーガレット(集英社 1963- 毎月5日20日発売)月2回刊)あるいはSho-Comi(小学館 1968- 毎月5日20日発売)月)などが発刊され漫画メディアは時代の主要メディアになっていく。そして、周知のように名称もコミック誌になり、テーマ別のコミック誌であるパチンコ、時代劇、ゴルフ、麻雀、釣り、など分化し、コミックマーケットという同人誌にまで進化していく。その進化の原点は1960年代にあったということである。
ちなみに1965年の「ハリスの旋風」を皮切りにマガジンの快進撃が始まり、「巨人の星」「あしたのジョー」の2大スポ根マンガで一気に少年雑誌としての地位を不動のものとした。その他にも「ゲゲゲの鬼太郎」「天才バカボン」なども連載を始め、1967年1月にはついに100万部を突破する。
新しい価値創造へと向かう70年代

1960年代は次の豊かさを実現するある意味環境づくり・助走の期間であった。その環境とは戦後生まれの団塊世代が本格的に働き、消費するという転換期を迎える。食べるために働いた時代で物の豊かさを求めた時代が60年代であったのに対し、70年代は物を求め物を満たすことが必要であった時代で、団塊の世代は「ニューファミリー」と呼ばれた。そして、今日を予見するような消費の「芽」が一斉に出てくる。
例えば、所得も増え単に物を満たすだけではない、そんな新しい価値をもった消費が現われてくる。1975年には便利さを売るセブンイレブンの1号店が誕生し、あのキャラクターのハローキティも生まれている。1976年には海外渡航者数が300万人を超える。こうした豊かさを背景に1980年代には多くの未来の芽が更に成長していく。
ファッション分野で言うと、80年代初頭には川久保玲や三宅一生さといった世界的なデザイナーによるデザイナーズ&キャラクターブランドが市場に新しい潮流をつくる。従来の男は男、女は女といった区別による考え方から、女性は男の良さを取り入れ、例えば肩パッドの入ったスーツを着こなし、男性は女性の柔らかなラインを取り入れたスーツを着るといった具合に。そうしたファッションの総称としてDCブランドと呼ばれ、セールを行う丸井には行列ができ社会的な注目を集める。つまり、物の価値がデザインといった情報的価値が求められていく時代の先駆けであった。
1980年代半ばそうした情報の消費を端的に表したのがロッテが発売したビックリマンチョコであった。シール集めが主目的で、チョコレートを食べずにゴミ箱に捨てて社会問題化した一種の事件が起きる。つまりチョコレートという物価値ではなく、シール集めという情報価値が買われていったということである。しかも、一番売れた「悪魔VS天使」は月間1300万個も売れたというメガヒット商品である。こうした現象も高度経済成長期ほどではないにしても安定成長となり、所得も着実に増え続けてきた背景がある。
「昭和文化」の爛熟期へと向かう
こうした消費変化を捉えたのがブランド戦略であった。モノ価値から情報価値への転換で、その中心は「女性」であった。1985年には男女雇用機会均等法が制定され、それまでの「女性らしく」あるいは男と女は違う」と言う旧来の固定観念が次から次へと変わっていく。DCブランドは更に個性的なブランドを生み出し競争はブランド間競争となる。そうした無名のブランド、小さなマンションメーカーと呼ばれたショップが原宿周辺に集まる。今日の竹下通りの原型がつくられていく。
こうしたファッションを中心としたテーマ集積を受けて、1980年代前半原宿の代々木公園横に設けられた歩行者天国で、ラジカセを囲み路上で踊るグループが出没する。次第に参加グループも多くなり、社会現象化する。いわゆる「竹の子族」の誕生である。1960年代銀座に集まった「みゆき族」に対し、踊りを組み込んだパフォーマンス集団へと進化していく。歩行者天国の廃止とともに竹の子族は消えていくのだが、ファッションの整地のポジションを確立していくこととなる。
1980年代は女性が社会という舞台に上がってきた転換期であった。団塊の世代はニューファミリーとして家庭づくりへと向かい、消費の舞台には上がってこなかったが、その下の世代は社会へと現われてくる。
この時代の空気感を作詞家阿久悠は沢田研二に「勝手にしやがれ」(1977年レコード大賞)を歌わせている。男と女の「すれ違い」をテーマとした歌である。
』 窓際に寝返りうって、背中できいている やっぱりお前は出て行くんだな・・・・・・』 別にふざけて 困らせたわけじゃない 愛というのに照れてただけだよ・・・・・・・
思い出していただけただろうか。後に阿久悠は「歌謡曲の時代」(新潮文庫)」の中で、”1970年代の男と女の気分が出ていると。更にその気分とは”真っ直ぐに、熱烈に愛することに照れてしまう”そんな気分を作詞したと書いている。

その象徴であると思うが、漫画家中尊寺ゆっこが描いたマンガで、従来男の牙城であった居酒屋、競馬場、パチンコ屋にOLが乗り込むといった女性の本音を描いたもので多くの女性の共感を得たマンガであった。その俗称が「オヤジギャル」。もう一つが物質的には満たされたお嬢様である二谷百合枝が郷ひろみとの出会いから結婚までを描いた「愛されれる理由」が75万部という1989年のベストセラーになる。つまり、物は充足するが何か心は満たされていない、そんなテーマの本であった。豊かさが次の段階へと進化してきたということである。新婚旅行から成田に帰国後離婚する華っぷりが多発し「成田離婚」として社会的な注目を集める。こうした背景には、女性からの一方的な期待、依存に応えることができないことが明らかになり、即離婚に移る女性が多く出現した結果でもあった。
昨年の東京オリンピック開催に際し、その理念とした多様性・平等といったことが話題となったが、既に1980年代においてその「芽」は出ていたと言うことである。
そして、1989年の暮れには株価は4万円近くにまで上がり、家計支出に占める食費や住居費といった生活必需品が50%を切り、娯楽や教育費の支出が50%を超える。後に「バブル期」と言われる時代である。
日本経済も日米摩擦はあるものの、造船竣工においては世界シェアー50%、半導体生産においても50%のシェアーを誇り経済は発展をしていた。そうした経済成長を背景に4月15日 に東京ディズニーランドが正式に開園する。また1987年にはリゾート法(総合保養地域整備法)が制定され、日本各地でいわゆるリゾート開発が行われる。多様な余暇産業が急速に進んだ。ゴルフ、スキー、マリーナ、リゾートホテル、といった大型施設を始めプール、スパ、ゲームセンター等が全国至る所で開発された。結果についてどうであったか、以前ブログにて書いたことがあるので今回は付け加えることはしないが、地方財政を悪化させ、過大なリゾート需要による実施、しかも画一的な開発によって・・・・・・・・・・結果は廃墟となり、いまなお野ざらしの状態の施設は多い。いわゆるリゾートバブルの崩壊である。こうした負の遺産も同時に起きていたことを忘れてはならないであろう。
なお、1989年4月初めての消費税3%がが導入される。このように日本経済が好調であったことから、大きな反対もなかった。
こうしたいわば転換期の日本については「転換期から学ぶ」(1)~(5)において主に生活価値観の変化、パラダイム転換について分析しているのでご参照ください。(後半へ続く)」
タグ :昭和文化考

